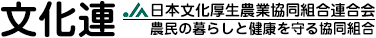協同組合の価値が問われる時代 食と医療福祉を守り、安心の地域づくりの実践を

新年を迎え、謹んでご挨拶を申し上げます。
昨年は、「令和の米騒動」と呼ばれる米価高騰が連日注目されるなか、米の需給の安定や水田農業政策の見直しが農政の大きな焦点になりました。JAグループとして、どのような役割を果たしていくべきか、地域農業の持続的な振興、消費者の理解など「食と農」をめぐって、多くの期待や激励が寄せられました。
病院・施設が経営悪化に苦しんでいる医療・介護については、賃上げや物価上昇に対する支援として緊急的な補正予算が措置されましたが、現在も厳しい状況が続いています。
人口減少・超高齢社会に対応すべく、国は「新たな地域医療構想」を推進しています。新たに設定する圏域ごとに病院の機能分化・連携、再編・集約化を協議、推進する計画であり、2040年に向けた圏域の医療提供体制が概ね確定していきます。農村部を中心に地域医療を支えている厚生連病院の医療機能や規模等の方向性が定まる重要な時期となってきます。
また、令和8年度の診療報酬改定では、機能分化・再編を前提としてメリハリをつけた評価が強まると言われています。医療の質や診療成果に基づく評価、生産性向上と医療DXの加速、選定療養の拡大等の新たな患者負担の導入が進むものと思われます。
このような会員を取り巻く情勢の大きな変化を踏まえて、文化連では今後の5か年を見据えた第11次中期事業計画を新年度よりスタートさせます。会員の「経営管理改革」支援をテーマに、新しい段階の共同購入事業・情報教育事業を柱としていきます。地域医療構想の本格化や地域包括ケアの構築を前に、厚生連医療・農協福祉が、地域に不可欠な存在として評価される質の高い医療・介護の提供と経営の健全化を実現し、持続的に発展していくための支援をさらに強化していく所存です。
共同購入事業においては、これまでの全国規模の廉価購入の取り組みに加え、会員本部・病院現場と本会担当者が一体となった「新しい共同購入」へのブラッシュアップを図ります。医薬品や医療材料等のメーカー・卸の協調的な高価格維持の姿勢が強まっています。厚生連の共同購入の取り組みは、農協法に基づき非営利原則で運営され、メーカーの過大な利益を適正化し、社会保険財政の健全性を確保する社会的意義を持つ運動であることの理解を広げながら、強化、発展させてまいります。
情報教育・DX支援事業では、JAグループ「人づくりビジョン」に呼応した情報教育機能の発揮に努めてきました。医師をはじめ多くの厚生連職員の方々にご活用いただいている「厚生連オンラインカレッジ」(Kカレッジ)の普及拡大と新規コンテンツの充実化、診療情報分析や物品・医事・原価計算の一体管理システムなどを通じた包括的支援を推進し、会員の「経営管理改革」をめざす協同の取り組みを進めていきます。
私たちは、国際協同組合年(IYC2025)を通じて、社会の分断や貧困・飢餓の解消、食料安全保障の確保など、世界的な課題の解決に協同組合が重要な役割を果たすことを確認しました。厚生連医療・農協福祉の協同事業の実践を通じて、「総合事業による組合員の豊かなくらしの実現」に貢献していきます。
文化連の役職員一同、引き続き会員の皆様のご期待に応えられますよう、今年も精一杯努めてまいります。
2026年1月
日本文化厚生農業協同組合連合会
経営管理委員会会長 八木岡 努
確信もって厚生連医療・農協福祉の運動・事業を進めよう ~4つの情勢をとらえる視点~

厚生連医療・農協福祉の現場で日々奮闘いただいている関係者のみなさんに対し、心から敬意を表したいと存じます。
医療・介護事業の急激な収支悪化をはじめ、事業環境はさまざまな面で混とんとしています。こうした時こそ、本質的な認識で情勢を把握し、運動と事業の方向性に確信をもって進んでいきたいものです。新年度の始まりにあたり、4つの情勢問題の基本的な見方に簡単に触れ、取り組みの課題を考えていきたいと思います。
保険料負担と財源問題の本質
第1に、医療・介護の財源問題と社会保険制度の改善課題についてです。
医療介護保障について、能力に応じた負担や公的保険の適用除外等が政策の基調に取り上げられています。すでに保険外併用療養費制度の対象拡大(長期収載薬)や介護施設利用者の負担増が実施され、高額療養費制度の負担上限引き上げ、市販品類似薬(湿布、風邪薬、胃腸薬等)の保険適用外し等の政策導入が議論されています。介護保険の利用料負担増、軽度の介護の市町村総合事業移行、ケアマネジメントの有料化等の方向も打ち出されています。一部野党の中には、「手取りを増やす」として保険料や税負担の軽減をワン・イシューとして叫び、そのかわり国民医療費4兆円削減や安楽死の法制化まで口にするところが現れ、社会保障制度の根幹が揺さぶられています。
社会保険財源の「改革」(削減)は、①被保険者の保険料と個人の税負担を増やす(公的な財布にお金を入れる構成を変える) ②保険の利かないサービス部分を増やす(財布の使い道を小さくする) ③老人医療と介護を別建ての保険に切り離す(別の財布にして高齢者負担を増やす)―の方策で進められていきます。高額療養費制度の負担上限引き上げは患者団体や多くの国民の強い反対で当面凍結となりましたが、政権「迷走中」と見せかけて、このうちの②の削減方策がどんどん進む懸念があります。
はたして、医療福祉の充実を求めることと、保険料・税負担を軽減することは相矛盾することなのでしょうか。より本質的な問題把握として、社会保険の原理について確認しておく必要があると思います。
資本主義社会の生活原則「自助」が成り立つ条件とは雇用と賃金の保障ですが、これが不十分だから格差・貧困が蔓延ります。そこで「自助」原則の部分的な修正として、国の責任で所得再配分のための社会保障政策(日本の医療・介護・年金では社会保険)が整備されてきました。
企業負担と租税の拠出割合を増やす課題
社会保険は民間保険と違い「加入と負担の強制+公的な資金投入」の社会原理で運用されます。その財源調達は、「賃金・勤労所得」「企業の利潤所得」「租税」(財政投入)の三者拠出です。企業が保険料負担をする意味は、労働者の労働力の再生産費用(老後および家族の生活費も含む)に見合った賃金が支払われず、追加的に企業が利潤として取得していた分(いわば賃金未払い分)から、保険料負担として強制支出させているものと言えるでしょう。国民医療費の負担割合(2021年度)は、被保険者と患者負担で40.4%、事業主21.6%、国と地方の公費38.0%となっています。
「賃金・勤労所得」から支払われる国民の保険料・税負担を軽減(高額所得者を除く)し、「企業の利潤所得」と「租税」からの拠出割合を増やしていくことが、社会保険財政を維持・拡大する基本です。その際、実質的に労働者である人・あった人の受け皿である国民健康保険や国民年金に企業負担がないことは大きな問題となってきます。社会保障に投入する「租税」が消費税(企業負担がない)中心とされていること、また、経営体力の弱い中小・零細企業と大企業との間で保険料負担の連帯調整(大企業の負担責任強化)するしくみが弱いことについても改善が必要です。医療福祉の側から、この視点での運動を広げることが、多くの国民・患者の共感を得ることにつながると考えます。
新しい地域医療構想に向けた病院経営管理の改革
第2に、新しい地域医療構想と病院経営管理の改革についてです。
令和6年度診療報酬改定は、医療機関に対して、機能分化・再編、効率的サービス提供へのさらなる深化を求めるものでした。とりわけ急性期医療の〝カタチ〟に大きな変革を迫る流れであり、急性期入院患者の厳格化により内科系を中心とする病院にとっては相当なダメージとなりました。
厚生労働省の2040年頃に向けた「新たな地域医療構想等に関する検討会」とりまとめ(2024年12月)は、「病棟の機能」に加えて「病院の機能」の報告を打ち出しました。「急性期拠点機能」「高齢者救急・地域急性期機能」「在宅医療等連携機能」「専門等機能」の4つに、病院そのものを〝振り分ける〟というものです。
「急性期拠点機能」の病院は、機能(手術件数、救急受け入れ数)によって施設数(たとえば構想区域に〇か所)を構想の中で定め、手術や救急医療等の医療資源を多く要する症例を他の病院からはぎ取って集約化するということのようです。「高齢者救急・地域急性期機能」の病院は、高齢者の救急搬送、入院後の早期リハビリ、早期の退院調整が中心とされ、病床数の絞り込みと看護体制効率化が迫られる可能性があります。今年度中に策定ガイドラインが示され、2026年度に都道府県計画が決まります。その後、構想区域において2027~28年度に協議し、決定させる予定です。
医療提供の抜本的効率化へ意識改革
同検討会では、少ない救急受け入れ数や低い病床利用率に不釣り合いな体制・給与費率を問題視しています。今後は、選択した「病院の機能」に応じた効率的な診療活動と体制に収れんさせていくことが必要となりそうです。さらに働き方改革により、短縮された労働時間で良質な医療を提供することが要求されます。効率が悪い医療は水準が低いと見なされます。医療水準を構成する最近の目標は、安全、効果的、患者中心、適時、効率的、平等とい言われています。
構想区域の再編協議の開始を待たず、今から個々の病院で、医療提供の抜本的な効率化を図る経営管理の改革が必須になります。2年後の構想協議と決定の段階で自院が埋没しないためには、健全経営を維持して質の高い医療を担う病院として地域で堂々と立っていなければならないからです。
医療提供の抜本的な効率化を図る経営管理とは、人材・設備の配置の効率化と集約化、医薬品・材料の適正な使用選択、医事管理や物品管理の適正化、意識改革と改革実行のための学習・研修インフラの整備等を進めることと言えます。診療情報・データ分析を高度化して、医師を含む全スタッフが意識改革を行い、一つの方向を向いた経営管理改革が、最大のテーマとなります。そして、そのことがスタッフの働きやすさと定着につながるものと思われます。
製薬企業等の過剰な利潤の適正化を
第3に、医薬品・医療材料等の高騰への基本的姿勢についてです。
原材料費や物流費・人件費の高騰を理由として、医薬品、医療材料、医療器械(保守料金を含む)のメーカーがこぞって値上げを進めています。しかし、この間の実態では、新薬メーカーをはじめ関係業界の大幅な利益増が顕著となっています。
国内製薬企業8社の2024年度上期決算では、平均で営業利益率15%、全体の営業利益の伸び率は80%にもなっています。欧米の製薬企業はさらに桁違いの儲けとなっており、純利益率30数%や純利益額百数十億ドルといった会社も少なくありません。しかもこの数値は、開発費や営業費(政府関係者・医師・弁護士等への不透明・不適切と指摘される工作費用を含む)を計上した後のものです。
厚生労働省は「医薬品流通ガイドライン」によって、新薬メーカーの利益拡大を後押しするかのように、医療機関との価格交渉を実質的に規制しています。アメリカからの薬価制度の改変の圧力もトランプ政権でさらに強まってくるでしょう。
文化連として、昨年末に「地域医療を守る医療経営を継続するため、医薬品の適正な価格交渉環境の確保を求める要請書」を厚生労働省に提出しました。一社流通・限定流通の無原則的な拡大の適正化や、不採算品再算定品の価格交渉の別枠扱いの撤廃と薬価優遇措置にかかる申請要件の厳格化等を強く訴えたところです。
独占価格の規制、社会保険財政健全化の運動としての共同購入
コスト増というもっともらしい理由による高騰を、単純にそのまま受け入れるわけにはいかないと思います。新薬メーカーは、「独占価格」「独占的超過利潤」の典型です。以前から、業界協調的な高薬価維持・流通支配、特許による競争排他的な独占販売が横行してきました。利潤の過剰分は、M&Aに投機的資金として回っている可能性もあります。企業買収でゲタを履かせて買った無形の価値等の「のれん」の対総資産比率は、ファイザー29.9%、武田35.8%にも上ります(2023年度)。製薬企業の過剰な利潤が、患者と医療機関の負担に付け回されているのです。医療の持続性確保のため、独占価格を規制し、医薬品を適切に値付けする薬価制度等を守る必要があります。
厚生連共同購入は、病院収支改善とともに、社会保険財政の健全性を確保する運動(市場実勢価格に基づく適正な薬価設定、製薬企業の利益の適正化、卸の本来の機能の適正評価)でもあります。こうした基本的な見方について会員のみなさんと認識を統一して、共同購入の拡大強化に取り組んでいきたいと考えます。
新しい認知症観、障害者定義による共生社会づくり
第4に、認知症基本法の施行と社会変化への先導的役割についてです。
認知症基本法が昨年1月に施行されました。新しい認知症観による共生社会づくりを理念に、認知症の人を「基本的人権を享有する個人」「社会の対等な構成員」とする考え方がベースに置かれました。当事者参画(意見表明、活動参画の機会)、予防対策偏重からの転換が法律に書き込まれました。バリアフリー化は生活サービス事業者の責務(合理的配慮)、「早期発見、早期診断、早期対応」と認知症の地域包括ケアシステム構築は国・自治体の責任と、明確化されました。
これに先立ち、国連で採択された障害者権利条約(2006年)は、障害者定義を見直し、「心身の機能の障害という個人的要因だけではなく、社会的障壁(たとえば周囲の差別や偏見、設備やサービスの使いにくさ)が要因となって、日常生活・社会生活への参加が左右され制限を受ける状態にある人」としました。日本では障害者基本法改正(2012年)や障害者差別解消法(2016年)が施行されています。とりわけ、行政や事業者が「合理的配慮」をしないことは差別になるとし、事業者にも法的義務(2024年)を課しました。しかし農協グループ内での受け止めは不十分な状況と言わざるを得ません。農協の信用・共済・購買・販売・利用・組合員活動のすべての仕事の現場で、サービス、取扱商品、施設・設備、配布資料等の総点検が急ぎ求められているのです。
本丸の医療や介護の業界でも、認知症基本法の成立・施行はあまり大きな話題となっていないように思われます。すでに多くの認知症患者・利用者を受け入れ、対応済みと考えてしまう傾向があるようです。認知症基本法は、医療福祉の専門職に向けても、「新しい認知症観」に基づくサービスの再検討を問いかけています。狭く認知症ケアを捉えて安易なラベリングにとどまっていないか、見直しの機会とすべきではないでしょうか。
人権重視の社会改革へ先導的役割
障害者差別解消法や認知症基本法が問うていることは、「人権」をめぐって社会が大きく変革・発展していく時代であることと受け止めるべきだと思います。障害者や認知症の人を、いわば当たり前に一緒に地域で暮らす人々として受け入れ、社会的障壁をなくしていく地域づくりへと急速に変わっていこうとしているのです。障害者差別解消法や認知症基本法が問うていることは、「人権」をめぐって社会が大きく変革・発展していく時代であることと受け止めるべきだと思います。障害者や認知症の人を、いわば当たり前にいっしょに地域で暮らす人々として受け入れ、社会的障壁をなくしていく地域づくりへと急速に変わっていこうとしているのです。
人権に始まり、長時間労働の是正、真に価値ある仕事(医療介護のエッセンシャルワーク等)への評価、ジェンダー平等、適正な商品価格・賃金、環境、平和…と、日本社会で変化せざるを得ない課題が、コロナを経てさらに早く表に出てきました。正義・適正・真の効率・創造的価値という「大義」が基本に座る社会への変革に応え、協同組合そして厚生連医療・農協福祉は先導的役割を果たせるのかが鋭く問われていると思います。
診療情報分析Pj、Kカレッジ「経営改革」コンテンツの新たな取り組み
文化連では新年度の事業計画案で、〈組織ビジョン2025〉学び呼びかけ合いつながる仲間づくり、〈事業ビジョン2025〉病院・施設経営の改革をめざす協同事業の実践、〈自己改革2025〉「ともにあゆみ、ともに支える」業務展開―とテーマを設定しています。
とりわけ、厚生連病院の経営改善は待ったなしの課題です。これに向けて、医薬品等の廉価購入・コスト低減と医療の質向上を進めるため、個々の施設の使用選択の適正化や物品管理の高度化にさらに踏み込んだ支援をしてまいりたいと思います。そのための診療情報・データ分析のプロジェクトの取り組みや、Kカレッジの新コンテンツ「経営管理改革と収支改善」編の開発・活用普及の強化を図ります。
会員のみなさんの引き続きのご協力をお願い申し上げ、新年度にあたってのご挨拶とさせていただきます。
2025年4月
日本文化厚生農業協同組合連合会
代表理事理事長 東 公敏