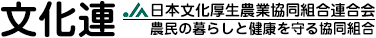厚生連の「協同組合ヒューマニズム」と「自主自立経営スピリッツ」
~戦後80年の夏、厚生連病院の歴史とともに考える~
日本文化厚生連代表理事理事長 東 公敏
先日、相模原協同病院(神奈川県厚生連)の創立80周年式典があり、参加させていただきました。同病院の開設は1945年(昭和20年)の8月1日、終戦の2週間前であり、まさに戦後80年を象徴する病院です。この機会に、他の多くの厚生連病院と同様に苦難の道を歩んできた同病院の歴史とともに、産業組合医療から引き継ぎ発展させてきた”背骨”というべきものについて考えてみたいと思います。
戦時下でも自主的運動として広がった産業組合病院
昭和初期から終戦までの間に、産業組合医療が成立していた状況は図のとおりです。現在の多くの厚生連病院の前身です。昭和初期に金融恐慌や大凶作が農村を直撃し、娘の身売り、欠食児童、一家離散、乳児死亡率の増加といった惨劇が発生しました。こうしたなかで、各地で雨後の筍のように「おらが病院」づくりが進められました。 産業組合の医療・保健事業が戦前の段階でここまで急速に拡大していたのはなぜなのか。真に農民の要求に基づく下からの自主的・民主的な社会運動、しかも農民の厚生・文化という生活部面まで視野に入れた協同組合事業をめざすという思いが強くあったからだと見ることができます。治安維持法の下では協同組合までもが危険思想としてレッテル張りされ、官憲により医療・保健に関わる産業組合関係者のいわれなき検挙・拘留が横行していた事実がそれを物語っています。
-800x663.png)
終戦直前に開院した相模原協同病院
太平洋戦争の戦況悪化が明らかとなった1943年から44年にかけて、産業組合は戦争遂行のための国家統制組織である農業会に統合されていきます。しかし病院設立の勢いは下火になるどころか、戦後の1948年に農業会が解散するまでの間にも、さらに広がっています。相模原協同病院と同じく終戦直前の1945年設立の病院としては、北信(5月、現長野県厚生連)、帯広(6月、現北海道厚生連)などがあります。
相模原協同病院の開院日の1945年8月1日と言えば、次の週には広島と長崎に原爆が投下されるという時期です。古材を近隣の工場や組合からかき集めて建設し、20床で同病院は船出しています。その竣工式の最中にB29爆撃機からの機銃掃射を受けたという記録が残っています。そんな極限の状況下でも、住民が熱望する病院をつくることの喜びが、上棟時の写真の笑顔から溢れ出ているように感じます。
劣悪を極めた結核まん延と無医村の増大
戦中・戦後の医療・健康をめぐる状況は、今の私たちには想像できない酷いものでした。
1939年の結核死亡者は15.5万人で、人口対比でドイツの4倍にのぼります。うち7割が15歳~39歳の青壮年層でした。徴兵検査の不合格者は、大正年間の平均で25%だったのが1935年には40%に激増しています。農村の医療は劣悪を極め、大正末期には2千カ所以下だった無医村の数が、昭和初期の1936年に3,243カ所にまで増大しています。
神奈川県の産業組合で病院の建設に第一に着手すべきと決定された地は、もっとも多くの無医村を抱えた県北(現在の相模原市域)でした。無医村解消の悲願が、戦時下に関わらず協同して行動することへと人々を突き動かしていったのです。
指導ではなく協同を呼びかけた産業組合の保健活動
戦前に、神奈川県の成瀬村(現伊勢原市)の詳細な健康調査に入った若い医学者がいました。東京帝国大学の医学生で、後に産業組合保健婦の指導に奔走し、戦後は北信総合病院(長野県厚生連)の院長を務めた小宮山新一です。彼は乳幼児・児童の4人に1人の栄養不良や、世帯の6割以上に上るトラコーマ罹患率といった不健康な状態に驚き、「ただちに村の問題解決に進まなければならない。私は報告書完成を待つことなくすでに撲滅の仕事に向かっている」と訴えました。直後に産業組合医療の全国組織から同村に再び派遣され、保健婦らとともに現地で保健指導にあたっています。
小宮山は、「国民学校の裁縫室を借りて、村を2班に分けて1回40人ほどで乳幼児相談の集まりをやった。最初は来る人は多くはなかったが、やがて全村の乳幼児がもれなく集まるようになった。母親たちは相談日を楽しみにしており、子どもの発育の様子や離乳食の作り方を話し合っている。訪問指導は、互いに助け合い補い合って行こうとする精神の発露でなければならない。保健婦ひとりが指導・援助するのではなく、村の人々全体が心を協せて(あわせて―原文ママ)助け励ましていくことである」と報告しています。
現代の厚生連・農協の健康管理活動は、この産業組合の農村保健運動を源としています。相模原協同病院は終戦後の間もない1949年に、すでに旧津久井郡の山間地で巡回健診を始めています。レントゲン撮影機をトラックに載せて巡回したことがNHKラジオで全国放送されたそうです。
患者との組織的同一性が医療者のヒューマニズムを発展させる
戦前戦後の苦難の時期を乗り越えて、どうして厚生連医療の先達たちは頑張れたのか。ひとつに「協同組合ヒューマニズム」があります。困っている状況をみんなで解決したい、目の前で苦しんでいる人を支え合いたいと、現代まで連綿と続いている厚生連医療の特質を「協同組合ヒューマニズム」と呼びたいと思います。
患者そして健康を願う人びとの出資と参加による医療活動であること、つまり患者との必然的な「組織的同一性」が基盤にあることが、医療者の「ヒューマニズムを感性的な段階から社会性を持った」強固なものへと発展させていくと説いたのが、金井満です。
金井は、戦前に産業組合中央会の中核として活躍し、戦後は文化連専務、その後、全国厚生連専務を歴任した人です。戦後に日本農村医学会の会誌で、「公立や他の公的病院はその経営主体の立場により民衆の生活圏外から与えられる上からの医療といえる。患者と組織的同一性がない」。医は仁術といわれるように医療者なら持っている「感性的ヒューマニズム」は、患者である農民(その代表による厚生連経営主体を含む)との一体性に基礎づけられた協同組合医療・厚生連医療においてこそ、さらに「高次の社会的なものに発展」させることができると書いています。「農民とともに」のヒューマニズムといえます。
コロナ対策や災害医療で発揮された「協同組合ヒューマニズム」
2020年からのコロナ禍ではその初発期から、多くの厚生連病院が他の病院に先んじて患者受入れを進めました。全国各地の厚生連のスタッフの思いと勇気ある行動の裏には、自覚するしないによらず「協同組合ヒューマニズム」のDNAがあったのだと思います。多くの組合員や地域の人々も、得体のしれない疾病ゆえの誤解や風評被害をはねのけて、厚生連の活動を励ましてくれました。
相模原協同病院では国内のコロナ患者の第1号に対応し、その後のダイヤモンド・プリンセス号の患者治療の中心的施設として活躍したことは記憶に新しいところです。
2024年の能登半島地震での医療支援活動でも「協同組合ヒューマニズム」がいかんなく発揮されました。神奈川県厚生連を含む全国の17厚生連から、延べ75隊464人がDMAT隊としてかけつけました。発災初期に活動したDMAT隊全体の、実に83%は厚生連病院だったことはあまり知られていません。厚生連医療は協同組合だから、離れた地域の被災者に対しても助け合いの精神で率先して動いたのです。
協同組合の伝統的・規範的な「自主自立経営スピリッツ」
もうひとつが、安易に”御上”に頼らない「自主自立経営スピリッツ」といえるものです。協同組合が伝統的、規範的に持っている基本姿勢です。
社会保障制度が全く未整備だった戦前の時代に、産業組合医療は経営確立のために、科学的で先進的な経営政策を実践の中から生み出してきました。大正期からの産業組合による自然発生的な診療所経営や開業医委託の限界性を早くから見抜いたうえで、採算確保と経営持続性に向けて、広域組合運営方式(戦後の連合会による病院運営方式につながる)、総合病院主義、予防・保健活動との連動を全国的な方針として掲げていたことは注目に値します。
さらに、医療費財源の社会保険的な共同負担の必要性、それによる医療経営の安定性確保を早くから展望していました。1938年に任意の国保組合運営による国民健康保険制度が施行されます。そこで産業組合(後に農業会)による「代行」の取り組みが全国的に広がります。終戦の時点では、全国の国保の3割強の地域で代行していましたが、戦後は国保事業の運営は市町村公営に一本化されてしまいました。
しかし産業組合による国保事業の代行の実践の経験は、むしろ現代において示唆的な意味を含んでいると思います。いまではお役所的に運営される市町村国保に対して、住民が主体者として参画している意識はほとんどないのが実態でしょう。わが国の医療は、被保険者みんなの保険料を中心として成り立つ社会保険の財政で運営されるのですから、被保険者・患者自らが適正な利用(真の意味での節約)を進める姿勢が求められるはずです。社会保険への公費負担の財源組み合わせの拡大は目指しつつも、被保険者による協同組合的な参画意識(主体的な健康づくりを含む)の醸成が決定的に重要であるという本質的な問題提起としてみることができます。
戦時下の接収圧力を毅然として跳ね除け
太平洋戦争の戦況が悪化する中で、官僚的医療統制を目論んだ日本医療団が発足(1942年)し、産業組合病院を接収するという強い圧力がありました。これに対して産業組合陣営は、国の健兵健民政策に協力するそぶりを見せつつ、したたかにそして毅然として抵抗をしています。
前出の金井を始め当時の関係者たちは、戦後に文化連で行われた座談会で述懐しています。「政府の衛生局長に向かって、農民はどうしても協同組織体でやらなければだめであり、戦争をやるにも自発的でなくては勝てないと話した」、「我々自身がつくり自分たちの血の通った施設なのだから、手放してはいけないという気持ちだった」、「あれほど戦時体制が強化されたにもかかわらず統合されないよう努力して動いた。あのあと特高に引っ張られた」。自主自立経営をまさに身を賭して見事に守ったわけです。
再出発時から苦しい財務。自主自立経営を旗印とした公的医療機関に成長
戦後の厚生連の再出発にあたって、混乱期の農業会時代の事業の欠損を、施設・設備の多い厚生連に負いかぶせて引き継がせる方針が取られました。欠損の多くが医療以外によるものでしたが、それを補うため資産の水増しが厚生連に押し付けられ、岩手や青森では自らの帳簿額の3倍にもなる譲渡資産額とされたといいます。この経営圧力に耐えかねたいくつかの県の厚生連では、県・市町村への病院の身売り・移管と解散が相次ぎました。
しかし、多くの道県の厚生連と農協グループは、ここでも「自主自立経営スピリッツ」を発揮して踏ん張ります。60年代に入って金井は、「経営が苦しくても厚生連として残った病院は英雄的だ」と言いました。
経営困難を乗り越えてきた厚生連病院の多くが、いまや公立の病院の代わりを務める堂々たる公的医療機関として発展しました。安易に補助金に頼らず効率的運営に努力する厚生連病院のおかげで、当該の自治体の負担は相当程度軽減され助かっていることは衆目の一致するところです。昨今では逆に公設民営で厚生連に任せる事例が出てきています。
相模原協同病院においても、戦後20年間ほどは経営赤字の苦難続きでした。1958年頃は大幅赤字や病棟焼失が重なり、真剣に市への経営移管が協議されたこともあったようです。このとき県共済連が、「生命の危険に備える共済事業と生命を守る厚生事業が相連携すべきだ」として、建て替えを全面支援し危機を脱したといいます。平成の中期には、医局の混乱により多くの科で医師の辞職が相次ぎ、巨額の損失を計上する時期がありました。しかし院長のリーダーシップのもと、若手医師たちが再建に結集し、3年でV字回復し「相模川の奇跡」と言われました。コロナ禍真っ最中の時期における新築移転(2021年)では、県内農協を挙げて増資等で支えています。
現在、厚生連に限らず多くの病院が赤字にあえいでいます。診療報酬の増額や救急・産科等の不採算医療への公的支援を求める運動の強化がますます求められます。同時に、少子高齢化と疾病構造の変化の中で、個々の機能分化に応じた施設運営の効率化・適正化、病院経営管理の改革は必須となってきています。「自主自立経営スピリッツ」を旗印とする厚生連医療が経営効率化・収支改善と医療の質向上に日々努力していることは、地域医療の維持・発展に不可欠なものとなっていくでしょう。
「歴史とは過去と現在の対話である」とE.H.カー(英国の歴史家)は言いました。本稿では、患者との組織的同一性に裏付けられた「協同組合ヒューマニズム」と伝統的・規範的な「自主自立経営スピリッツ」が、戦時中も貫かれ、戦後の厚生連に引き継がれてきたこと、そしてそのことが、住民合意に基づく地域医療再編が医療機関に求められる現在において決定的に重要となっていることを見てきました。命とくらしを破壊する戦争への道を絶対繰り返さないためにも、戦後80年のこの夏、会員の皆さんとごいっしょに確認し合いたいと思います。
参考
- 『激動の70年―相模原協同病院開院70周年記念誌』(同病院 2015年)、『コロナを克服し次の100年に向かって―相模原協同病院開院80周年記念誌』(同病院 2025年)
- 小宮山新一「神奈川県成瀬村における健康調査速報」(日本労働科学研究所『農業労働調査書報告』№ 50 1939年)
- 「農協医療事業の推移と問題点(座談会)」(日本文化厚生連『農村医療パンフレット』 1956年)
- 金井満「医療農業協同組合理念の発展について」(『日本農村医学会雑誌』第10巻第4号 1963年)
- 『協同組合を中心とする日本農民医療運動史』(全国厚生連 1968年)
- 黒川泰一『砂漠に途あり 医療と共済運動50年』(家の光協会 1975年)
- 『産業組合中央会史』(全国農協中央会 1988年)
- 鈴木俊彦『協同人物伝―農協をつくった人々』(全国協同出版 1997年)